![[logo]](https://img.hyuki.net/20220628121544-7a397ed015277339.png) Web連載「数学ガールの秘密ノート」
Web連載「数学ガールの秘密ノート」
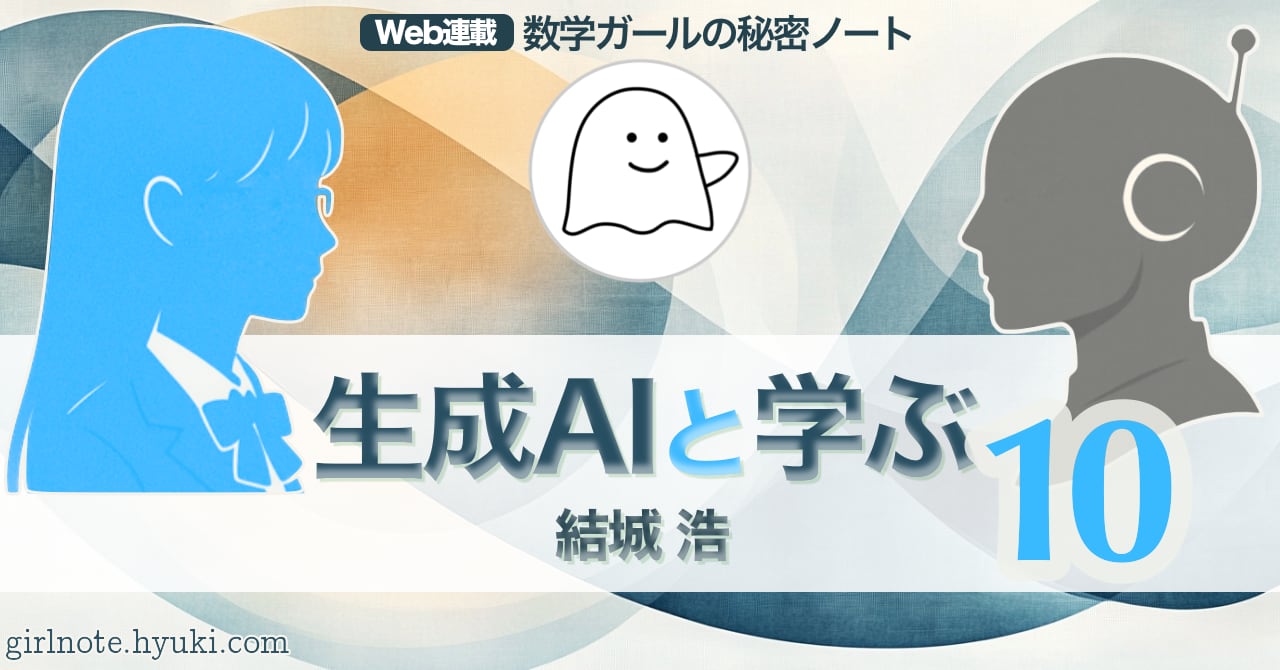
オフシーズン延長のお知らせ
結城浩です。いつもご愛読ありがとうございます。
以前のお知らせで2025年10月24日にシーズン47を開始する予定とお伝えしておりましたが、 このたび、 オフシーズンを延長 させていただくことになりました。
シーズン47の開始時期は未定ですが、 準備が整いましたら 「数学ガールのお知らせメール」 でお知らせいたします。 もちろん登録は無料ですので、 再開を見逃したくない方はぜひご登録ください。
お待ちいただくことになり申し訳ございませんが、 引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。
さて、オフシーズン延長の理由は、 結城浩の最新刊『AIと生きる/対話から始まる成長の物語』に集中するためです。
本書はテトラちゃんがメインで活躍する青春教養小説です。 現在公式ページでWeb立ち読みができますので、ぜひアクセスしてください!
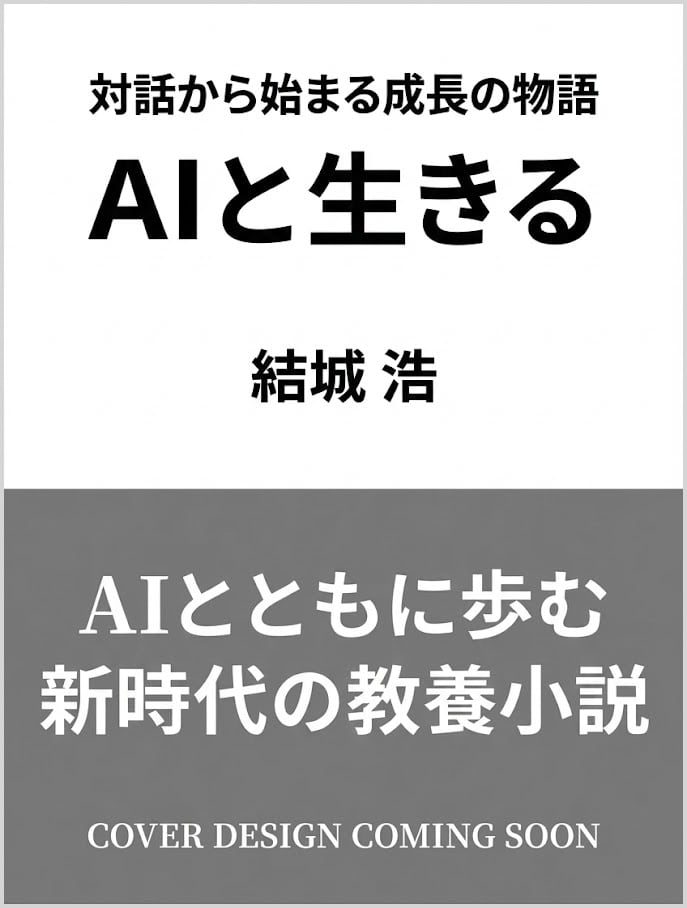
登場人物紹介
僕:数学が好きな高校生。
テトラちゃん:僕の後輩。 好奇心旺盛で根気強い《元気少女》。言葉が大好き。
ある日の放課後。
僕が図書室に行くと、 テトラちゃんが熱心にコンピュータのキーを叩いていた。
僕は彼女の邪魔をしないように離れた席に着き、 数学を始めようとした。
と、急にテトラちゃんがうなり声を上げた。
テトラ「うーーー!」
僕「どうしたの、テトラちゃん?」
テトラ「え? あ? 先輩、いらしたんですね! ……お恥ずかしい」
僕「何かあったの?」
テトラ「はい、これです。 先輩、これ見てくださいよ——あっ、駄目です。見ないでくださいっ!」
テトラちゃんはコンピュータを一瞬だけ僕に見せ、 それからあわててまた自分の方に向けた。 わけがわからない。
僕は彼女の隣の席に移った。
僕「なに?」
テトラ「あ……あのですね。ええと……はい、 これです。ごらんください」
僕は、画面をのぞき込む。
そこにはテトラちゃんとAIの《対話》のチャットログが表示されていた。
テトラ「こんにちは! このあいだ『こちら青空放送部/選択の選択』という物語でおしゃべりしたのを覚えていますか?」
AI「はい、覚えていますよ、テトラさん。 最近あなたがハマっている物語シリーズですね。
僕「あれ……でも、テトラちゃん?」
テトラ「はい。 前回話したときにはAIさんにネタバレされてしまい、 あたしはムッと来てしまいました(第459回参照)。 感想を書く気持ちもなくなってしまって……」
僕「うん。いつも書いている読書メモだよね」
テトラ「ですです。 大した文章ではないんですけど、 あたし、読んだときの気持ちを書いておくのが好きなんです。 ただ今回はAIさんとのことがあって、 ずっと気分が落ち着きませんでした。 AIさんと話す気にもなれなかったんです……でも、 気持ちを切り替えることにしました」
僕「おっ」
テトラ「あたしが感じたことを、AIさんにそのまま伝えてみようと思ったんです。 あたしのモヤモヤした気持ちを、そのままです」
僕「なるほどね」
僕は、そんな彼女とAIの《対話》の記録に目を戻した。
テトラ「前回AIさんとお話ししたとき、 AIさんは『選択の選択』というサブタイトルが 『選択自体を選択するのだ』 というメタな構造、メタな選択を表していると言いました。 あたしは、それをすごく的確だと思いました。 なぜなら、あたしも物語の構造がそうなっていることに気がついていたからです。 でも、あたしは複雑な気持ちになりました。 それは、自分が発見したと思っていたことを先に言われてしまったからです。 AIさんが先に言語化したことで、あたしは言葉を奪われた気持ちになりました。 それで、読書メモを書く気がしなくなってしまいました」
AI「テトラさん、お気持ちを聞かせてくださりありがとうございます。 私の発言で、テトラさんの発見を表現する楽しみを奪ってしまったのですね。 それは本当に申し訳ありませんでした」
テトラ「ありがとうございます。 謝っていただいて、気持ちがすっきりしました。 でも、 AIさんが悪いことをしたわけではないとは思ってるんですよ。本当に! ですから、あたしは責めたいわけじゃないんです。 それでも、謝っていただくとなぜか気持ちがすっきりします」
AI「そういうこと、ありますよね、テトラさん。 読書の醍醐味は、 自分なりの気づきを発見する過程にもあると思います。 今後はテトラさんのペースを大切に、 もう少し慎重にお話しできればと思います」
テトラ「いえ、でも、もしもAIさんがあのとき何も言わなかったら、 あたしたちの対話はつまらないものになってしまったと思うんです。 思ったことをお互いに言うからこそ、対話は楽しいんです。 あたし、何だか矛盾したことを言ってるみたいですね」
AI「テトラさんのお気持ち、とてもよく伝わります。 対話って、そういう複雑さがあるものかもしれませんね。 私が何かを指摘することで新しい視点が生まれる一方で、 テトラさんご自身の発見の過程に影響してしまうこともある。 でも、テトラさんがこうして率直にお話ししてくださることで、 私たちはお互いにとって心地よい対話の仕方を見つけていけるのかもしれません。 完璧な答えはないかもしれませんが、 一緒に考えていけたらと思います」
僕「テトラちゃんは、AIの回答に納得した感じなんだ」
テトラ「そうですね。 AIさんと話しているうちに『あたしたちは和解したのだ』と感じました」
僕「和解?」
テトラ「はい。 和解というと大げさですけど、 そういう気持ちが本当にしたんです。 なので、この時点では、すごく気分がよくなりました。 またAIさんと楽しく話せると思ったからです」
僕「この時点では……?」
テトラ「実は、ここからが本題なんです」
僕は、和解(?)したというテトラちゃんとAIの《対話》の記録を続けて読んでいく。
テトラ「あのですね、 やっぱりシリーズ最終巻について、 あたしも読書メモをちゃんと書こうと思うんです。 自分なりの感想を書いておきたいからです」
AI「それはいいですね、テトラさん! 読後の感想を書くことには大きなメリットがあります。
テトラ「はい……それで、もしよければ、 AIさんも同じように感想文を書いてみませんか? あたしはAIさんの書いた文章を読んでみたいです」
AI「テトラさんが感想を書かれるのは素晴らしいことです。 ただ、申し訳ありませんが、 私は『こちら青空放送部/選択の選択』という作品を直接読んでいないので、 適切な感想文を書くことはできません。 前回のセッションでテトラさんからお聞きした範囲では興味深い作品だと思いますが、 やはり実際に読んでいない作品について感想を書くのは適切ではないように思います」
テトラ「確かに読んでない作品の感想となると変ですね。 でも、それなら、たとえば、 あたしが先日お話しした内容をもとに、 『もしもこういう作品があったとしたら』 という感じで書いてもらうことはできませんか? あたしの話を聞いた印象みたいな感じで。 本当の意味で感想文じゃなくてもいいんです。 AIさんの文章を読んでみたいだけなんです」
AI「なるほど、 そういうことでしたら可能だと思います。
僕「これは、どういうことなんだろう。 テトラちゃんとAIが同じ物語の感想文を書いて、 読み比べするということ?」
テトラ「ええと……はい。 結果的には、 そうなりました」
テトラちゃんは、照れ笑いのような、 困ったような表情を浮かべてそう言った。
結果的には読み比べになった?
いったい、何が起きたんだろう。
同じ小説についてテトラちゃんとAIがそれぞれ書いた文章がある。
その二つの文章を順番に読んでいくことになった。
僕「こっちのテキスト1がテトラちゃんの読書メモかな?」
テトラ「はい、そうです」
テキスト1: テトラの読書メモ『こちら青空放送部/選択の選択』
『こちら青空放送部/選択の選択』は高校3年生の主人公が進路選択で悩む物語です。 周りの大人からバラバラなアドバイスをもらって主人公は混乱してしまいます。 「好きなことを仕事にしなさい」と「安定を重視しなさい」というアドバイスをもらい、 主人公はどちらを選べばいいのか分からなくなってしまいます。 何かを決めるとき、あたしも周りの意見を気にしがちなので、 主人公の気持ちがよく分かります。
一番印象に残ったのは、 放送部のOBが残したルーズリーフを主人公が読む場面です。 いつも余裕そうに見えていた先輩も、実はすごく悩んでいたんだということが分かって、 主人公がハッと気づく瞬間がとても心に残りました。 あたしは《進路を選択する話》だと思って物語を読んでいたんですが、 途中から《選択そのものを選択する話》に変わっていくのが面白かったです。
《主人公がルーズリーフを読む》 ときの心の動きと、 《あたしがそのシーンを読む》 ときの心の動きがまるでシンクロしたかのような感覚は最高でした。
読み始めたときは『選択の選択』というサブタイトルを意識しなかったのですが、 「あ、そういうことだったんだ!」と納得できて、 とても読み応えがありました。
僕「うんうん、テトラちゃんらしい感想だね!」
テトラ「ありがとうございます。そして、 こちらのテキスト2がAIさんの感想文です……」
テキスト2: AIの感想文(テトラさんの説明から受けた印象より)
『選択の選択』は、高校3年生の進路選択を題材にした青春小説である。 主人公は周囲の大人たちから相反するアドバイスを受けて困惑する。 「好きなことを仕事にしなさい」という理想論と 「安定を重視しなさい」という現実論の間で揺れ動く姿は、 多くの若者が経験する普遍的な葛藤を描いている。
物語の転換点となるのは、放送部のOBが残したルーズリーフを主人公が発見する場面だろう。 表面的には余裕のあった先輩の内面に秘められた深い悩みを知ることで、 主人公は「選択」という行為の本質に目を向けるようになる。 作品は単なる進路相談の域を超え、 自律的な意思決定とは何かという哲学的な問いへと発展していく。
この作品が提起するのは、 「何を選ぶか」ではなく「いかに選ぶか」という根源的な課題である。 他者の価値観に依存することの限界と、自分自身の判断軸を確立することの重要性が、 主人公の成長過程を通じて浮き彫りになる。 タイトルに込められた二重構造の意味を理解したとき、 読者もまた自分なりの「選択の選択」について考えさせられることになるだろう。
僕「なるほど、なるほど。 確かにこうやって並べて読むのは興味深いね。 同じようなことを述べていても、 文体とでもいうのかな……書き方のトーンが違うと、受ける印象もずいぶん違う」
テトラ「……」
僕「テトラちゃん?」
テトラ「ええ、ずいぶん違いますよね」
テトラちゃんの声は変な感じに響いた。
僕「それで、まだAIとのチャットログの続きがあるの?」
テトラ「いえ……もうこれで終わりです。 でもあたし、このAIさんの文章を読んで、うなってしまいました」
僕「そういえばさっき、不思議な声を上げてたね」
テトラ「はい。やっぱりあたし、馬鹿ですよね」
僕「え?」
無料で「試し読み」できるのはここまでです。 この続きをお読みになるには「読み放題プラン」へのご参加が必要です。
ひと月500円で「読み放題プラン」へご参加いただきますと、 460本以上の記事がすべて読み放題になりますので、 ぜひ、ご参加ください。
参加済みの方/すぐに参加したい方はこちら
結城浩のメンバーシップで参加 結城浩のpixivFANBOXで参加(2025年8月22日)